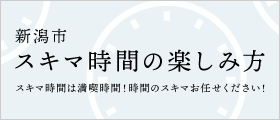令和7年4月17日 市長定例記者会見
最終更新日:2025年4月22日
市長定例記者会見
| 期日 | 令和7年4月17日(木曜) |
|---|---|
| 時間 | 午前10時00分から午前10時53分 |
| 場所 | 新潟市役所(本館3階 対策室) |
発表内容
- ◎令和7年度のスタートにあたって
- 1.市立保育園・認定こども園「紙おむつ等サブスク」の導入
- 2.子どもの権利相談室こころのレスキュー隊
- 3.新潟市ひとり親世帯に対する物価高騰対策給付金支給事業
- 4.米国関税措置等に伴う特別相談窓口の設置
- 5.その他
質疑応答
- 市立保育園・認定こども園「紙おむつ等サブスク」の導入について
- 新潟市ひとり親世帯に対する物価高騰対策給付金支給事業について
- 米国関税措置等に伴う特別相談窓口の設置について
- 子どもの権利相談室こころのレスキュー隊について
- 柏崎刈羽原発について
- 市内中心部のまちづくりについて
- 古町地域(西堀ローサ、旧三越跡地)について
- 市役所旧分館について
- 新規採用職員の内定辞退について
- 県内自治体で開催されたイベントの波及効果について
- 市内中心部の落書き被害について
配布資料
市長記者会見動画
令和7年4月17日開催記者会見の動画(クリックすると録画映像をご覧いただけます)(外部サイト)
![]()
発表内容
◎令和7年度のスタートにあたって
おはようございます。新年度になりましたので改めてよろしくお願いします。
新年度ですので、ひと言抱負をごく簡単に述べさせていただきます。
昨年1月1日に発生しました能登半島地震から約1年3カ月が経過しましたが、先月21日には、避難指示を出しておりました西区大野を最後に、すべての避難指示を解除しました。
また、大きな被害を受けておりました坂井輪中学校では、この4月から、ようやく1年生から3年生まで全学年が揃って同じ敷地内で学校活動が再開されました。
その他、道路・下水道の復旧、公費解体などについても、着実に取り組みを進めております。
しかし、住宅や生活再建が進まず、不安を抱える被災者の方々が依然いらっしゃいますので、地震から2年目の復旧・復興に向けた取り組みは、今年度も市役所が全力で取り組む最優先の課題です。
これからも、被災者の皆さまに寄り添い、生活再建の支援や、公共インフラの復旧などを着実に進めてまいります。
同時に、いつ起こるか分からない今後の災害に備えた安心・安全なまちづくりを進めていきます。
また、急速に人口減少が進んでいますが、そうした中でも経済活力を生み出し、市民所得を向上させるため、地域の外から消費や投資を呼び込む取り組みを進めます。
国内ではインバウンドが増加していますが、本市においても、外国人観光客のさらなる誘客を促進したいと考えています。
併せて、新潟駅周辺整備を着実に進め、本市の拠点性をさらに向上させ、人々が行き交う活力あふれる新潟市の実現を目指します。
そして、本市の発展には将来を担うこどもの存在が欠かせません。
こどもを産み育てたい方々の希望を実現できるように、そして、こどもたちが健やかに成長していけるように、子育てや教育への支援も一層充実させていきます。
今年度も国内外から、選ばれる都市新潟市となるよう精一杯取り組んでいきます。
1.市立保育園・認定こども園「紙おむつ等サブスク」の導入
それでは、発表案件に移らせていただきます。
最初に、市立保育園・認定こども園における「紙おむつ等サブスク」の導入についてです。
現在、市立園を利用しているこどもが使用する紙おむつは、各家庭でこどもの名前を記入し、持参していただいていますが、保護者にとっては、手間がかかることや、登園時の荷物が多くなり負担となっています。
子育て市民アンケートおいて、子育てで負担に感じることとして、「生活にゆとりがなく時間に追われる」ということが最も多くなっております。保護者の負担を少しでも減らすことで、こどもと接する時間を増やせるように、紙おむつ等の定額利用サービス、サブスクを7月から導入します。
今後、市が選定した5者の中から、保育園ごとに保護者が投票により実施事業者を決定していただきます。
このサービスを導入することで、園の職員にとっても、園児ごとのおむつの在庫管理や補充などの連絡にかかる業務の軽減につながると考えています。
詳細につきましては、配付資料のとおりです。
多くの方からサービスを利用していただき、各家庭では、こどもと触れ合う時間が増え、保護者とこどもたちの笑顔につながる取り組みにしていきたいと考えています。
2.子どもの権利相談室こころのレスキュー隊
次に、子どもの権利相談室こころのレスキュー隊についてです。この相談室は、令和6年8月に設置をし、この4月で開設から9カ月を迎えました。
この相談窓口が、こどもたちから、より親しんでもらえる窓口となるよう、このたび、マスコットキャラクター「ここうさ・ここねこ」の着ぐるみを新たに作製しましたので、ここで皆さんに紹介をさせていただきます。
今後、こちらの「ここうさ・ここねこ」が各地のまつりや、こども向けイベントなどに出向き、相談窓口のPRをいたしますので、よろしくお願いいたします。
子どもの権利相談室では、こどもやこどもに関わる大人など、これまでに39人(令和7年4月14日現在)の方から相談を受け、それぞれの相談に対し、子どもの権利救済委員、子どもの権利相談・調査専門員が一つ一つ丁寧に対応し、240回ほどのやり取りを行っています。
それにより、悩みを抱えるこどもが、普通に学校生活を送れるようになったなど、問題解決につながっています。
4月から新生活が始まった方も多いと思われますが、新しい生活に慣れなかったり、環境の変化についていけなかったりして、心身の不調を訴えるお子さんもいらっしゃるかもしれません。
子どもの権利相談室は、権利侵害だけでなく、こども自身が困っていること、悩んでいることなど、様々な相談に応じ、こどもの最善の利益が図られるよう、問題の解決に向け、相談者と一緒に考え、活動する窓口ですので、お子さんが悩んでいること、困っていることがあれば、ぜひお気軽にご相談いただきたいと思います。
なお、子どもの権利推進週間の初日となる5月5日には、新潟市こども創造センターで行われるイベントに「ここうさ・ここねこ」も参加いたします。
当日はキャラクターの塗り絵やグリーティングなど、こどもたちに楽しんでいただけるイベントを用意しておりますので、多くの皆さまからご来場いただきたいと思います。
3.新潟市ひとり親世帯に対する物価高騰対策給付金支給事業
次に、「新潟市ひとり親世帯に対する物価高騰対策給付金支給事業」についてです。
物価高騰の影響で経済的に苦しい状況に置かれているひとり親世帯に対しまして、新潟市独自の取り組みとして、給付金を支給します。
支給対象は、令和7年3月分の児童扶養手当受給世帯等のうち、2月より実施している「令和6年度住民税非課税世帯支援給付金」の対象とならない世帯です。
1世帯あたり3万円に、こども1人につき2万円を加算して支給します。対象世帯は約2,450世帯を見込んでおり、うち、児童扶養手当受給世帯で該当する約2,200世帯については、申請不要で支給いたします。
申請不要の対象世帯には、4月11日に案内ハガキを発送しており、4月28日に同手当の受給口座に振込予定です。
また、一部、公的年金などの受給により児童扶養手当の支給を受けていない方は申請が必要になりますので、5月中旬以降に申請の受付を開始し、随時支給する予定です。
4.米国関税措置等に伴う特別相談窓口の設置
次に、米国関税措置等に伴う特別相談窓口の設置についてです。
昨今の米国関税措置等の動向により、市内企業の経営の影響に対応するため、特別相談窓口を新潟IPC財団で開設いたします。
相談は、事前予約制で土日・祝日を除く9時から16時までとなっており、窓口では、相談内容に応じて経営相談や融資制度の案内等を行います。
今後の米国関税措置等の動向にそれより、影響を受ける市内の企業の皆さまからは、必要に応じてご利用いただければと思います。
5.その他
案件は以上ですけれども、このほかに2点お知らせをさせていただきます。
最初に、先日開幕いたしました「大阪・関西万博」についてです。配布資料のとおり、本市も新潟県催事へ共同出展を行い、本市が誇る食や伝統工芸品などの特産品を広く発信し、本市の交流人口の拡大につなげていきます。
国内での万博開催は20年ぶりで、多くの国・地域が出展いたします。大変貴重な機会ですので、市民の皆さまからも足を運んでいただければと思います。
また、来週末からは、ゴールデンウイークが始まりますが、本市でも様々なイベントが開催されます。
各イベントの詳細は配布資料のとおりです。市のホームページにも掲載しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
市民の皆さまはもちろんですけれども、多くの皆さまが新潟市にお越しいただくことを期待いたしております。
質疑応答
市立保育園・認定こども園「紙おむつ等サブスク」の導入について
(新潟日報)
まず、紙おむつのサブスクについてなのですけれども、関川村やほかの自治体でも少しサブスクが広がっているかと思うのですが、新潟市ならではというか、新潟市の特徴みたいなものというのはあるでしょうか。
(市長)
新潟市ならではの。
(新潟日報)
例えば5者から選べる、おむつを投票で選べるとかあったと思うのですけれども。
(市長)
それはほかではないのですか。
(佐藤幼保支援課長)
ご利用いただく方に納得いただいた上でと考えておりますので、5者から選んでいただくということは特徴の一つかと思っております。
(新潟日報)
実証実験を行ったということですけれども、その結果というのでしょうか、5者で好評だったのでしょうか。
(佐藤幼保支援課長)
ホームページでも公表させていただいております。数は9園と少なかったのですけれども、好評をいただきまして、9割以上の方がまた利用したいということで回答を頂いております。
(新潟日報)
この紙おむつについて市長ご自身はどのような効果を期待されるのか、改めてお願いいたします。
(市長)
先ほどもお話しましたけれども、子育て世帯の負担を少しでも軽減して、時間と心にゆとりを持っていただき、こどもと過ごす時間を多く持っていただくことによって、こどもたちの笑顔と健やかな成長につながるよう期待しているところです。
(新潟日報)
今回の対象は、市立の園となっていますが、私立の園に今後拡大したりとかそういったことは想定されていますでしょうか。
(市長)
私立については、既にかなりやっていると聞いております。新潟市で使用する紙おむつについては、主に0歳から2歳児になると思われますけれども、市立園には約1,700人が在園しており、そのうち利用を希望する園児ということになります。
新潟市ひとり親世帯に対する物価高騰対策給付金支給事業について
(新潟日報)
ひとり親世帯に対する物価高騰対策給付金についてお願いいたします。今回は対象がひとり親世帯、住民税非課税の対象とはならない世帯とありますけれども、今後、この給付金事業について対象者を拡大するお考えというのは現時点であるでしょうか。
(市長)
現在のところはありませんけれども、物価高騰に苦しんでおられる方がたくさんおられると思いますので、現状を注視しながら、今後の対応については考えていきたいと思います。
(新潟日報)
改めてですけれども、この時期に支給をされるという狙いというか、理由は何なのでしょうか。
(市長)
やはり、新年度、こどもにお金がかかるというようなこともあって、この時期に支給をさせていただくということになります。
(新潟日報)
物価高騰対策、お困りの市民も大変多いと思うのですけれども、こうした給付金事業のほかに市として何か支援策というのは考えているのでしょうか。
(市長)
今年度予算では、市民の皆さんに対してはクーポン券(プレミアム付商品券)を、民間の事業者と連携しながらクーポン券を発行して、現在、物価高騰に苦しんでおられる方々の支援に充てたいと思います。
米国関税措置等に伴う特別相談窓口の設置について
(新潟日報)
いわゆるトランプ関税に関する特別相談窓口設置についてなのですけれども、現時点での相談件数はどのくらいあるのか。相談内容も分かりましたら教えていただければと思います。
(市長)
相談窓口のほうは設置をさせていただきましたけれども、相談は今のところないと聞いています。
(新潟日報)
それこそ、相互関税を気にかけている企業、市民が大勢いると思うのですけれども、新潟市として、こうした相談窓口設置のほかに何か施策というか、考えていらっしゃるでしょうか。
(市長)
まずは、どういう影響が新潟市内の事業者の皆さんに出てくるかということをしっかり把握するということが大事になるのではないかと思います。想像ですけれども、新潟市内で輸出をしている企業といいますと、お米ですとか、酒ですとか、機械関係、自動車部品関係のような関連産業じゃないかなと思っています。
(読売新聞)
先ほど市内事業者による米だったり、酒だったりというお話でしたけれども、先行きが不透明な中で注視していくというお話でしたけれども、市内の経済に対する影響の大きさというのはどれほどとお考えでしょうか。
(市長)
なかなか市内企業にどのくらい影響があるかというものは、今現在予測できませんけれども、新潟県のアンケートの調査の数字ということになりますが、新潟県輸出入状況・海外進出状況調査によりますと、令和5年の新潟県全体の対米輸出額が約406億円となっているそうです。国別で見ますと、中国、韓国、台湾に次いで4番目で、輸出総額が約8パーセントとなっております。市内企業につきましては、先ほど申し上げましたように、米や日本酒、電子部品、医療部品などを扱う企業があるといった状況です。
(読売新聞)
先ほどの数字というのは県全体の数字ということですが、市内ですとどれくらいというのは。
(市長)
市内でというのがちょっと把握できておりませんが、長期的に見ると、輸出製品の原材料等を供給している企業などの国内取引においても影響が拡大することが懸念されます。そうしたことで、今回、新潟市におきましても相談窓口を設置させていただいたということです。
(NST)
トランプ関税の特別相談窓口の相談相手というのは、IPC財団のどういった立場の方になるのでしょうか。
(荒井産業政策・イノベーション推進課長)
IPC財団の経営相談の専門人材、プロジェクトマネージャーになります。
子どもの権利相談室こころのレスキュー隊について
(新潟日報)
こころのレスキュー隊の「ここうさ・ここねこ」でしょうか、市長から見て感想を率直にお願いします。
(市長)
あれは、こどもたちが描いてくれたものを今回着ぐるみにしたわけですけれども、こどもたちから親しんでもらうために着ぐるみを作りましたので、大変かわいらしいものができたなというふうに感心しています。
(NHK)
基本的な相談の件数とかが増えているのかどうか、傾向をお伺いできればと思います。
(市長)
相談件数39件ありますけれども、年代別の内訳は、小学生に関するものが13件、中学生が13件、高校生が10件、18歳以上が1件、そのほか不明が2件となっております。相談の方法は、ウェブフォームが21件、電話が17件、対面が1件となっております。相談内容については、これまで受けた相談内容のうち、こども自身の心身の悩みに関するものが最も多いです。続いて家族関係、対人関係に関する悩みとなっています。
(NHK)
この39件というのは、設置されてからこれまでですか。
(市長)
実施(設置)されてからこれまで、そうです。
(TeNY)
こころのレスキュー隊に関してなのですが、これは相談を受けるだけなのか、それとも、その後の何か支援につなげていこうというものなのでしょうか。
(市長)
子どもの権利相談室は、独立性を持った子どもの権利救済委員が、市の他の機関などと調査や調整活動を行うということがありますし、子どもの権利救済委員、こちらは弁護士が相談に乗っていくという形になります。それぞれ相談を受け、弁護士の場合は、その後も相談に乗ってあげ続けるというか、そういう活動になろうかと思っています。
柏崎刈羽原発について
(新潟日報)
昨日から柏崎刈羽再稼働の県民投票に関する県議会の審議が始まりましたけれども、知事が二者択一では県民の意見を把握できないとおっしゃっていて、昨日の審議では自民党が県民投票に慎重だという姿勢を示して、野党系は実現を求めているという形になっていますけれども、現状、議論をご覧になっていて、市長としてどうお考えか、まずお聞かせいただけますでしょうか。
(市長)
直接、テレビ等の放映を見ているわけではありませんけれども、県民投票条例案に対して推進している積極的なほうと、慎重に考えておられる議員の方々双方が活発に議論を展開されていると認識しております。
(新潟日報)
市長ご自身としては、今回の県民投票条例案に対する、現在、賛否等のお考えは持ち合わせていらっしゃるでしょうか。
(市長)
私は現在、県議会で審議中ですので、その内容については、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。
(新潟日報)
知事が多様な民意を把握できないと言っている中で、知事としては明確に賛否を示していませんけれども、その点についてはどうご覧になっていますか。
(市長)
今回は県民投票条例の審査ということで、必ずしも賛否を表す必要性はないのではないかと思っています。
(新潟日報)
昨年の会見のときに、再稼働を求めるような中央の動きに対して、時期尚早だとおっしゃっていましたけれども、今もそのお考えに変わりはないですか。
(市長)
現在も再稼働に向けた議論の材料を揃えている段階ですので、今もその考え方に変わりはありません。
(新潟日報)
ここ最近でもまた電気関係の火災とかも相次いでいますけれども、その辺、東電の安全確保の甘さだとか、そういったところには懸念等はございませんでしょうか。
(市長)
今回の発煙ですとか、火災による外部への影響はないと聞いておりますけれども、東京電力においてはこうしたトラブルがたびたび発生しており、そのことによって市民、県民の不安が起こってまいりますので、東京電力におかれましては、こうしたトラブルがぜひ発生しないように最善の努力をしていただきたいというふうに思います。
市内中心部のまちづくりについて
(TeNY)
最初の抱負のほうに新潟駅周辺の賑わいというお話もあったと思うのですけれども、万代広場が少し遅れていると思うのですけれども、その中でどうやって賑わいをつくっていくかということについてお伺いしたいです。
(市長)
万代広場につきましては、都市の庭をコンセプトにして、これから八つのそれぞれ、新潟市は8区ありますので、8区の花壇を作って花を植えたり、そして、新潟駅の構内と結ばれる広いスペースができますので、そこでさまざまなイベントなどに活用できることになりますので、今後完成した暁には有効に、賑わいにつながるようなことにつなげていきたいと思っています。
(TeNY)
INPEX新潟ビルディングで進出報告会が開かれたと思うのですけれども、若者の流出が課題となる中で新潟駅前の開発が今進んでいて、今後どのようなことが期待できるか、お伺いしたいです。
(市長)
まずは、かなりの数の企業が「にいがた2km(ニキロ)」に進出をしてきてくださいましたので、新たな雇用も生まれました。現在、新潟市においても、新潟市から県外に出ていく方々が多いわけですので、ぜひそうした雇用が生まれましたので、新潟市に留まってくれる人たちが少しでも増えていただければというふうに思っています。
(NHK)
中心部のまちづくりに関してなのですけれども、万代とか上所とかでマンションの建設が進んでいて、賑わいが生まれる期待もあるのですけれども、外国人が投資目的で買っていたり、専門家の先生にお伺いしたところ、人口減少の状況を見ると過剰なのではないかというようなご意見も頂いたのですけれども、市長としては、今、中心部にマンションが建ってきている状況をどのように見られていますか。
(市長)
たしかにご指摘もごもっともな部分はありますけれども、建設する事業者の皆さんも全くデータ、根拠なしに建物を建てているというふうにも思われませんので、我々としては、業者の皆さんもさまざまなデータのもとに立地のいい場所に建てているのだろうと思っています。また、例えば上所駅が新たにできましたけれども、そうした周辺が駅の設置に伴って活性化をしていくということについては、市としても喜ばしいことだと思っています。
古町地域(西堀ローサ、旧三越跡地)について
(NHK)
先月末に営業を終了した西堀ローサについてなのですけれども、今後、どのようなスケジュールで活用方法を検討されていくかということと、新潟地下開発(株式会社)に貸付金9億円出されてると思うのですが、その返済をどうするのか、お伺いします。
(市長)
これからの活用の仕方ですけれども、施設単体ではなく、将来の古町エリア全体の中でローサのあり方というものを考えていきたいというふうに考えております。ご質問の中で、活用(を検討)する中で、ここまでで見えてきた課題ということでお話をさせていただくと、不動産業界やディベロッパー、コンサルタント会社などからご意見を伺い、その助言では、古町エリアには歴史的な街並みや個性豊かな飲食店など、駅前や万代とは異なる魅力があると評価いただいています。一方で、古町エリア全体の将来像がはっきりしない中で、西堀ローサがビジネスとして成立できる環境であるかなど判断が難しく、時間をかけて検討しなければならない案件だとのご意見もいただいているところです。また、本市が行いました老朽度調査結果では、調査対象の約350カ所のうち9割以上の設備が修繕、更新が必要な状態であることが判明いたしまして、具体的な活用には老朽化によるハード面の課題や、地下施設であるという特殊性による制約など多くの課題があるというふうに認識しております。そうしたことから、西堀ローサの将来の活用については、今後、さまざまな方々とさまざまな角度からの検討を積み重ねる必要があり、相当な時間を要すると見込まざるを得ないというふうに考えております。
新潟地下開発株式会社の債権についてですけれども、この貸付については債権放棄をせざるを得ない可能性が高いというふうに考えており、現在、その対応については検討を進めているところです。債権放棄の時期については、同社の解散とその後の清算に向けた手続の進捗を見つつ、適切なタイミングで判断したいと考えています。
(読売新聞)
先ほど不動産業界の方だったりから、古町全体の将来像というものを見越してでないと、なかなか活用方法も含めて検討は難しいというお話でしたけれども、古町でいうと、三越跡地も今事業が少し行き詰まっているような状態だと思うのですが、ローサの活用方法の検討だったり、再開発も含めて、そことの歩調を合わせていかないと難しい。そのため、相当な時間を要するということなのでしょうか。
(市長)
頂いたご意見の中には、そういうニュアンスを含んだご意見もおそらくあったものというふうに思いますし、それのほかに、先ほど申し上げました西堀ローサが老朽化によって修繕や更新を必要とするところがたくさんあって、多額の費用を要するというような課題もあるというふうに思います。
(読売新聞)
三越跡地に関していえば、今、工事を請け負ってくれる業者を探すのに難航していて、計画自体も実現可能性というところも含めて検討されていると思うのですけれども、そこと全く別で、ローサというのは検討が進んでいくわけですか。
(市長)
それとは全く(別で)。我々としては、それとはまた別に検討はしたいと思っていますけれども、現実問題として、先ほど申し上げた、私たちが頂いた業界の専門家の皆さんからは、やはり周辺の古町全体の将来像が見えないとなかなかそこに出ていく方というのはいらっしゃいませんよねというようなことを頂いているところです。従って、いずれにしても、現実的に修繕、更新に相当な時間を要しますし、本当にそこに我々も修繕、更新の費用を投じられる価値あるものがそこで実施できなければ、市として税金をかけることもできないというふうに今は認識しているところです。
(新潟日報)
先ほどローサの件で、9億の債権放棄しなければいけない可能性が高いとおっしゃいましたけれども、ちょっと驚いたのですが、税金が、9億の債権を放棄するということに対して、当時の貸付の判断であるとか、市としての対応に関してどういうふうに責任を感じていらっしゃるかということをお聞きしたいのですけれども。
(市長)
責任の取り方については、私も当時の9億を貸し付けた経緯だとか推移については、当時は市長ではなかったので承知しておりませんけれども、いずれにしても責任の取り方については、今後、検討はしていきたいというふうに思います。
(新潟日報)
ご自身として責任をということですか、それとも貸付判断に関して調査をするとか。
(市長)
過去に遡ってもしょうがありませんので、最終的には、もし責任ということがあるとすれば、私ということになるのだろうというふうに想像はしています。
(BSN)
活用方法についていろいろな検討に相当な時間がかかるというところ、債権放棄についてもそのタイミングを計っている状況ということなのですが、今後のスケジュール感として、今年度はどのような予定で動くだとか、何か分かっていることはありますでしょうか。
(市長)
ローサについて今年度ということになると、引き続き関係者の皆さんからご意見をお伺いしたいというふうに考えています。
(BSN)
今年度は関係者から意見を聞く。
(市長)
あとは、ローサの歩道をしっかり維持していくということになるかと思います。
(BSN)
市有化はいつごろになる予定ですか。
(市長)
今のところ、6月議会で議案を提出できるよう、これまでは準備を進めてきております。
市役所旧分館について
(新潟日報)
今、解体が始まった旧分館なのですけれども、あちらは本館の将来的な移転用地とするとされていて、それまでの間、暫定的な活用が可能とされているかと思うのですけれども、跡地活用については、今どういう検討段階にあるのか。また、どういった観点を重視されて今後検討されていくのかをお伺いしたいと思います。
(市長)
今おっしゃられたとおりですけれども、建物耐用年数が65年ということですので、おおむね令和36年以降をめどに、ここの本館の建て替えが想定されています。本館の建て替えまでの25年間の暫定的な活用、これについては、現在検討を進めているところです。ただし、暫定的な利用ですので箱物の整備は考えておりませんが、旧分館跡地につきましては、周辺に文化施設ですとか、スポーツ施設がありますので、多くの人の流れや賑わいづくりにもつながるような整備を検討していきたいと考えています。
(新潟日報)
検討にあたっては、庁内での検討ということになるのでしょうか。ディベロッパーを入れてというのは。
(市長)
まずは庁内での検討ということになります。令和7年、令和8年度2カ年かけて検討していきたいというふうに考えておりまして、施設の整備の開始は、早くて令和9年度になるのかなと思っています。
(新潟日報)
分館について1点確認したいのですけれども、先ほど令和7年度、8年度の2年かけて庁内で検討するというお話でしたけれども、それは分館の敷地に関してということなのか、それとも周辺の、今後廃止も検討されている新潟市体育館とかあの辺のスポーツ施設も含めてのことなのかというのはいかがでしょうか。
(市長)
分館の敷地のみについてです。
新規採用職員の内定辞退について
(BSN)
新年度が始まったタイミングということなのですけれども、新潟市職員内定者の17パーセントが辞退したということがありまして、今後このようなことが続くと、市政運営が大変だなと思うのですが、採用対策、現時点でのお考えがあればお聞かせください。
(市長)
現在人手不足ということもありまして、志願する方については新潟市役所1カ所ではなくて、いくつかの併願を行っているのではないかと思います。そういう中での辞退ということもあるのではないかというふうに思います。新潟市としましては、いずれにしましても、現在の人手不足の中でできるだけ能力の高い職員を採用できるように、やはり働きがいのある、そして魅力のある新潟市役所づくりに努めていきたいというふうに思っております。また働く環境の整備も同時に行っていかなければならないというふうに認識しています。
(BSN)
具体的なところというのはどのようなお考えですか。働きがいのある職場づくり。
(市長)
難しいですね。やはり市の職員がそれぞれお手本を示してあげて、市役所の職員というのは市民の皆さんに奉仕する非常に尊い仕事なんだと認識をしていただければうれしいです。
県内自治体で開催されたイベントの波及効果について
(新潟日報)
先週末、近隣の新発田市で人気アイドルグループの大規模なライブイベントがあったかと思います。玄関口の新潟を経由して大勢のファンの方が新発田に行かれたり、逆に戻って来られて新潟周辺での観光を楽しんだりということもあったかと思うのですけれども、市長として、詳しい数字ですとかは出ていないとは思うのですけれども、盛り上がりの波及効果について新潟市としてどのように受け止めていらっしゃいますか。
(市長)
先般、新発田市でイベントがあったようですけれども、1日は天候の関係で中止になったということですけれども、12,000人の方々が集まって、大変盛り上がりを見せたということです。新潟市を経由して新発田に行った方も多数おられると思いますので、新潟市にもそうしたイベントを県内で開催していただくことによって、新潟市においても波及効果はあったものと思っております。
(新潟日報)
近隣の自治体ですとか県内の自治体で大きいイベント、催しがあった際に、同じ県内自治体として協力して誘客を図ったり、相乗効果を狙ったりというところも交流人口の拡大とかそういったところで大事になってくるかと思うのですけれども、市長のお考えを伺います。
(市長)
今、お話しいただいたように、新潟市で開催するときのみならず、新潟駅を通過する皆さんが多数いるとすれば、やはり新潟市も協力してそういうイベントを盛り上げていくということは必要になってくるのかなというふうに思いますので、今後、どういうことができるか検討してみたいと思っています。いずれにしましても、いろいろな有名な方々が新潟の朱鷺メッセを使っていただいて、非常に駅から近いということで、たくさんの方々が新潟でライブをしていただけるということは、新潟に大きな経済的な効果があるというふうに思っておりますので、大変ありがたく思っております。我々も県などと協力しながら、今後もより多くの方々が来ていただけるように努めてまいりたいというふうに思います。
市内中心部の落書き被害について
(NST)
今月4日に新潟中央署管内で落書きの逮捕者が出て、警察が萬代橋の落書きとの関連性を捜査しているということがありましたが、市内中心部で落書きが続いていくつも見つかっている、被害を受けている建物が続々と出ているという点について、市長のお考え、受け止めをお伺いできればと思います。
(市長)
今回の新潟市内の数カ所にわたる落書き、もしかしたら同じ方なのでしょうか、非常に残念に思っております。萬代橋は新潟市が誇る橋でもありますし、新潟市の中心部の商店の壁面のあたりに大きな落書きを描いて行ってしまうという方々は、絶対そういうことはやらないでいただきたいというふうに思います。また、そうしたことによって美観を損ねて、都市の価値も落ちていくと思いますので、我々もしっかり今後の対策、どういうことができるのか、国道事務所の皆さんなどと連携して、再発防止に努めていきたいと思っています。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()

 閉じる
閉じる